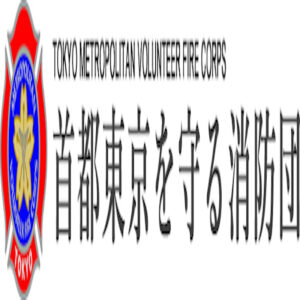消防団員・防災士としてのレビュー
ごきげんよう
本日は日本消防会館でのシンポジューム「地域総合防災力の発揮」大会に参加させていただき、私自身、消防団員および防災士として改めて感じたことがあります。それは、地域防災力を高めるためには、地域住民の「主体的な参加」と「継続的な協力」が欠かせないということです。




地域防災力の充実に向けて
- 住民の主体性が鍵
岩手県一関市藤沢町の事例は、地域住民が主体的に防災活動に取り組むことで、強いコミュニティが形成されることを示していました。消防団の活動でも感じることですが、住民一人ひとりが「自分ごと」として防災意識を持つことが、災害時の迅速な対応につながります。最後に婦人消防協力隊・隊長のお言葉の中で特に印象的であった「災害から学ばさせていただいている」という言葉の意味を深く考えさせられるとともに私の心に強く響きました。 - 情報伝達の重要性
愛知県豊橋市の取り組みで紹介された「きこえない・きこえにくい人への理解が深化した地域づくり」は非常に印象的でした。消防団として活動する中で、災害時に情報が届かない住民がいることが課題だと感じています。手話言語や文字情報(絵カード・ピクトグラム)など、多様な情報伝達手段を活用し、すべての人に必要な情報を届ける仕組みを作ることが防災力向上につながります。 - 地域の特性に応じた防災計画
島根県の半島防災の事例では、地域特有の地形や環境に合わせた防災計画が紹介されました。私たち消防団も、地域の特性を理解し、住民と行政が連携して対策を進める必要性を感じています。地域ごとの課題を共有し、さらに離れた地域に於いての災害等事例を学びそれをそれぞれの地域の特性に置き換え具体的アイデアを出し合い行動(訓練)につなげることが重要です。
消防団員としての使命
消防団は、地域防災の最前線で活動する存在です。災害時だけでなく、平時から地域住民と連携しながら防災訓練や啓発活動を行うことが私たちの使命です。今回の大会を通じて、以下の点を改めて強く感じました:
- 地域住民との信頼関係の構築
防災活動は、住民との信頼があってこそ効果を発揮します。日頃の訓練やコミュニケーションを通じて、住民との絆を深めることが大切です。また、知らない人でも自分よりも助けを必要としている人に手を差し伸べることのできる地域づくり。 - 継続的な学びと改善
災害は予測できない部分が多くあります。そのため、今回のような大会に参加し、最新の防災知識を学び続けることが消防団員としての責務だと感じています。
今後の取り組み
消防団員・防災士として、地域防災力をさらに高めるために以下の活動を進めていきたいと思います:
- 防災訓練の強化
地域住民が主体的に参加できる訓練を企画し、防災意識の向上を図る。 - 情報保障の充実
災害時に情報が届かない住民をゼロにするため、手話言語や多言語対応を含む情報伝達手段を導入する。 - 地域特性に応じた計画の策定
地域の地形や環境に応じた具体的な防災計画を住民とともに作り上げる。
今回の大会は、地域防災力を高めるためのヒントがたくさん得られる貴重な機会でした。消防団員・防災士として、学んだことを現場で活かし、地域の安全を守るために尽力していきたいと思います。
ごきげんよう
#街の笑顔を守りたい
文責:京橋消防団広報編集委員団本部