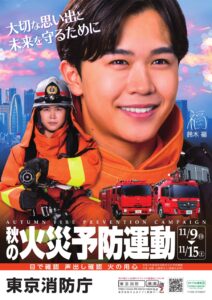『御巣鷹山の事故 突然の別れと向き合う40年』のご講演を聴講し
ごきげんよう
1985年8月12日、日本航空123便が群馬県御巣鷹山に墜落し、520名もの尊い命が奪われたあの日から40年が経ちました。この悲劇は、今も多くの人々の心に深い傷を残しています。
京橋消防団山本昌由氏は、当時父親を失ったお一人です。お父様がご家族に持って帰ろうとしていたお土産の無惨にも炭化した焼き菓子を思い出し、鞄の中で見つかったそれを目にしたときの心情を語る姿が、胸を打ちつけました。この事故は、家族との突然の別れ、そして生き残った4名の奇跡的な生存者の証言を通じて、多くの教訓を私たちに残しています。
事故の原因と教訓
事故の原因は、技術研究・捜査機関による公式な発表では後部圧力隔壁の破損でした。当該航空機により1978年に発生した「尻もち事故」の際の、製造元であるボーイング社による圧力隔壁の整備不良との見解です。この修理ミスによって強度が不足した隔壁が金属疲労で亀裂が入り、飛行中に破壊されたことで、機内の空気が流出し、垂直尾翼が吹き飛んで操縦不能に陥ったそうです。この構造的な欠陥と整備不良が不運にも重なりそれが引き金となり、機体は制御不能に陥りました。事故当時、日本と米軍による捜索活動の遅延に於いては主導権を巡り議論していたことも口伝により語られています。生存者の一人では残念ながらなかったのですが、「僕、頑張るぞ」と言葉を残した男の子の存在は、事故当時ご存命であった乗客に勇気と元気を与えていたことが、今も多くの人々の記憶に刻まれています。
この悲劇を繰り返さないためには、過去の教訓を未来に伝えることが重要です。現在、山本昌由氏が立ち上げた非営利一般社団法人メモリーリンク1985が中心となり、事故の教訓を伝える活動や再発防止に向けた取り組みが進められています。生成AIを活用した動画発信やアニメーションによる教育コンテンツの制作も行われています。これらは、国内外問わず多くの人々に事故の背景や教訓を伝える新しい手段として注目されています。
テクノロジーの進化と遠隔慰霊
近年では、テクノロジーの進化により、御巣鷹山への「遠隔慰霊登山」が可能になりました。WiFi通信やスターリンクを活用することで、現地に行けない人々も慰霊の気持ちを届けることができます。また、ストリートビューやSNSを活用した情報発信も広がりを見せています。X(旧Twitter)では、事故をテーマにした漫画やアニメが多くの人々に共有され、若い世代にも事故の教訓が伝わるようになっています。
防災への応用:未来の備え
御巣鷹山の事故から学び、私たちは現在や未来の災害にも備えなければなりません。ご講演の中では様々な災害に対する備えも交えた内容を述べていました。例えば、富士山噴火や首都直下地震といった大規模災害への対策です。富士山噴火が発生した場合、1〜2時間で東京にも降灰が到達すると予測されています。降灰量に応じた呼吸器疾患への対策や、降灰予報を活用した備えが重要です。ゴーグルやマスクの準備、降灰対策サイトの活用など、日頃からの備えが命を守ります。
また、阪神淡路大震災の数倍から数十倍ともいわれる首都直下地震が発生した場合、被害を最小限に抑えるためにテクノロジーを活用した防災教育や動画コンテンツの発信が求められます。
未来へのメッセージ
御巣鷹山の事故から40年が経った今、私たちは過去の教訓を未来に繋げる責任があります。悲しい事故を繰り返さないために、事故の記憶を風化させず、次世代に伝えていくことが大切です。
「メモリーリンク1985」や生成AIを活用した防災向け動画は、事故の歴史を語り継ぐだけでなく、未来の災害に備える新たな手段として期待されています。
私たち一人ひとりが過去を学び、未来に備える意識を持つことで、悲劇を防ぐ力になるのですね。
ごきげんよう
#街の笑顔を守りたい
文責:京橋消防団広報編集委員
団本部
Archives ~